
営業時間 : 9:00~18:00

営業時間 : 9:00~18:00
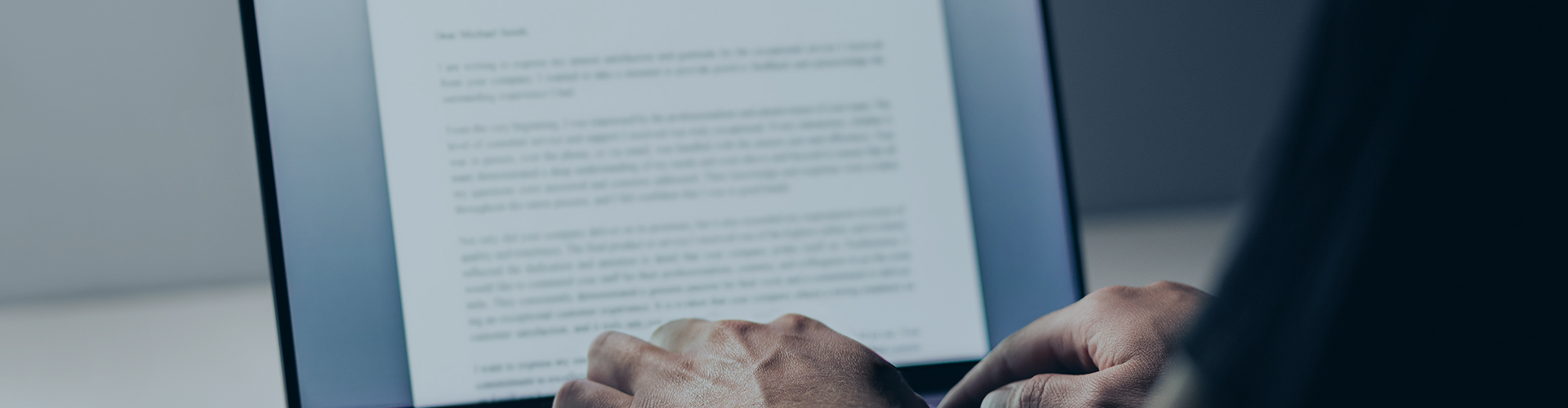
コラム
今回は、企業型確定拠出年金(企業型DC)についてご説明いたします。この制度は、社員や役員(以下「社員等」)の老後資金準備の方法として、会社が福利厚生の一環として導入できる「企業年金制度」です。
本コラムでは、企業型DCの制度概要に加え、税制面・社会保険面でのメリットについても整理いたします。
________________________________________
1.制度の概要
確定拠出年金は「確定拠出年金法」に基づき実施されている制度で、その趣旨は「国民が老後資金を自主的に準備することを支援し、老後の生活の安定と福祉の向上に寄与する」ものとされています。
確定拠出年金には 個人型(iDeCo) と 企業型(企業型DC) があり、掛金を拠出して運用し、老後に受給する仕組みは共通ですが、加入者が「個人」か「企業」かによって制度設計や税制・社会保険上の取扱いが異なります。
企業型DCは会社の福利厚生制度の一環として、会社が社員等のために毎月掛金を拠出し、社員等がその資金を運用して老後資金を形成するものです。
掛金の原資は次のいずれか、またはその組み合わせとなります。
① 会社が全額を負担する。
② 社員等が任意で給与の一部を拠出する(選択制)。
③ 上記①、②の併用。
掛金額は原則として年1回変更が可能です(規約により異なります)。
加入できるのは、会社が規定する社員等のうち70歳未満かつ厚生年金被保険者であ
ることが要件です。
________________________________________
2.拠出できる金額(上限)
掛金の拠出限度額は以下のとおりです。
① 他の企業年金制度がない場合 … 月額55,000円
② 確定給付型企業年金等と併用する場合 … 月額27,500円
________________________________________
3.受給できる金額と時期
社員等は拠出金を運用して積み立てた資金を60歳以降に受給できます。ただし、制度加入期間が10年以上あることが条件です(加入開始時の年齢によって必要加入期間は5年以上~10年以上と異なります)。
________________________________________
4.受給方法と税制上の取扱い
受給は以下の方法を選択できます。
① 一時金で全額受給 … 所得税法上「退職所得」として課税
② 分割で受給(年金形式) … 「公的年金等に係る雑所得」として課税
なお、年金形式で受給した場合には所得に応じて「高齢者医療の自己負担割合」に影響する可能性があります。
(例:70歳以上は通常2割負担ですが、「現役並み所得者」と判定されると3割負担
となります。)
________________________________________
5.企業型DCとiDeCoの違い(税制・社会保険面)
企業型DCとiDeCoはいずれも確定拠出年金制度に基づきますが、拠出時の税・社会保険上の取扱いが異なります。
(1) 選択型企業DCの場合
• 掛金は 給与から控除されるため、給与総額から拠出額を差し引いた金額を基に税・社会保険料を計算します。
(例:給与40万円、拠出額5万円 → 計算基礎額は35万円)
(2) iDeCoの場合
• 掛金は給与からではなく手取り給与から拠出します。
税・社会保険料は拠出前の給与額を基に計算されますが、拠出額は年末調整または確定申告で所得控除の対象となります。
________________________________________
6.制度のメリット
企業型DCの主なメリットは次のとおりです。
① 掛金は法人税法上、全額損金算入が可能 → 法人税等を軽減できる。
② 選択型企業DCでは社員等の社会保険料を軽減できる。
③ 会社の社会保険料負担も軽減できる。
④ 役員も加入可能(役員1名の会社でも導入可能)。
________________________________________
7.制度のデメリット
一方で、以下のようなデメリットもあります。
① 制度運営に事務コスト(口座開設費・管理費等)がかかる。
② 社員等に対する投資教育の実施が必要。
③ 拠出した資金は60歳まで引き出せない。
________________________________________
8.おわりに
今回は企業型DCの概要についてご説明しました。
確定給付型企業年金やiDeCoなど、類似する制度も存在しますので、別の機会に解説
いたします。
制度の詳細や導入方法、具体的な設計については、ぜひ当事務所へご相談ください。
________________________________________
最後に
本コラムの内容は 令和7年8月31日現在の法令 に基づいて作成しております。平
易な表現を心がけておりますが、一部、法律上の定義とは異なる場合があります。
また、税務上の取扱いは実態や取引形態によって異なる場合があり、個別の検討が必要です。
制度に関して不安をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。