
営業時間 : 9:00~18:00

営業時間 : 9:00~18:00
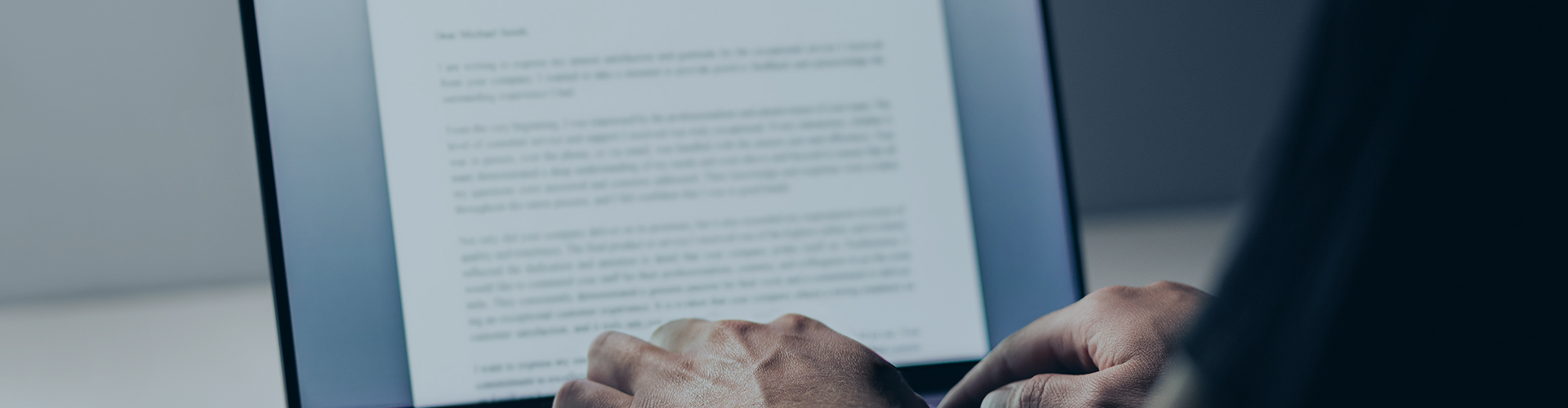
コラム
向笠文崇税理士事務所を開業して早くも5ヶ月が経過し、ようやく事務所の体制なども落ち着いてまいりました。
今後、不定期ではありますが、企業経営を中心としたコラムを掲載してまいります。
今回のテーマは給与に係る年間の税務、社会保険の内容と手続きについて概要を説明させていただきます。
1 源泉所得税
原則として、給与の支払日の翌月10日までに納税が必要となります。そのため、
給与の支給がある場合は、毎月納税が必要となります。
ただし、給与の支払いを受ける人数が常時10人未満であり、かつ税務署に「源泉
所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合には、年の上半期と
下半期との年2回に分けての納税が可能となります。
①1月から6月支給給与に対する源泉所得税:7月10日までに納税
②7月から12月支給給与に対する源泉所得税:翌年1月20日までに納税
2 住民税
源泉所得税と同様に、給与の支給日の翌月10日までに納税が必要となります。
ただし、給与の支払いを受ける人数が常時10人未満で、各市区町村に「特別徴収
税額の納期の特例に関する申請書」を提出している場合には、2回にまとめて納税が
可能となります。
①6月から11月支給給与に対する住民税:12月10日までに納税
②12月から翌月5月支給給与に対する住民税:6月10日までに納税
3 年末調整
役員や従業員等から扶養控除申告書等の提出を受けた場合、それらの者に対し次の
手続きを行います。
①扶養控除申告書等に基づいて、所得税の年間税額を計算します。
②年間税額から期中に給与から徴収していた源泉所得税の合計額を差引きます。
③つぎの区分に応じて、徴収または還付を行います。
・年間税額が源泉徴収額を上回る場合:差額分を追加で徴収
・年間税額が源泉徴収額を下回る場合:差額分を還付
④翌年1月31日までに、役員や従業員に源泉徴収票を交付します。
(扶養控除申告書等の提出がない者も含む。)
4 給与支払報告書の提出
年末調整の結果について各市区町村に「給与支払報告書」を提出します。
これにより、市区町村は、誰が、どこで、どれくらいの年収を得ていたのか確認し
その結果を基に年間の住民税を計算し、5月頃に給与支払者に給与から徴収しなけれ
ばならない税額を通知します。
5 法定調書合計表の提出
法定調書合計表とは、1月から12月までに支払われた給与や家賃、税理士等への
支払額合計を記載する書類となります。
「合計表」ですので、その明細もあり、「支払調書」と言います。支払内容ごとに
一定の要件を満たす場合には、こちらも併せて提出が必要となります。
この書類は1月31日までに税務署に提出します。
6 労働保険申告書
労働保険申告書は毎年6月1日から7月10日までの間に、4月1日から翌年3月
31日までの労災保険および雇用保険の申告・納付を行う手続きです。
申告書はつぎのいずれかに提出となります。
①金融機関:そのまま納付も可能です。
②管轄の労働局又は労働基準監督署:納付は金融機関窓口で行います。
なお、納付は(手続きが必要ですが)口座振替によることもできます。
7 社会保険の月額算定基礎届
健康保険、介護保険、厚生年金について4月から6月の標準報酬月額を基に毎年
7月10日までにまでに届出書を提出し、社会保険料の徴収額の決定がなされます。
決定された金額は9月から翌年8月までの各月に適用され、給与から社会保険料を
徴収し、毎月末に納付を行います。
なお、決定された社会保険料については、(残業手当が多くなるなど)標準報酬月
額に2等級以上の変動が生じる場合には、随時「被保険者報酬月額変更届」を提出し
保険料額を変更する必要がありますので、ご留意ください。
これまでの内容を取りまとめるとつぎの図表のとおりになります。
内容について確認したい事項がございましたら、いつでもご連絡ください。